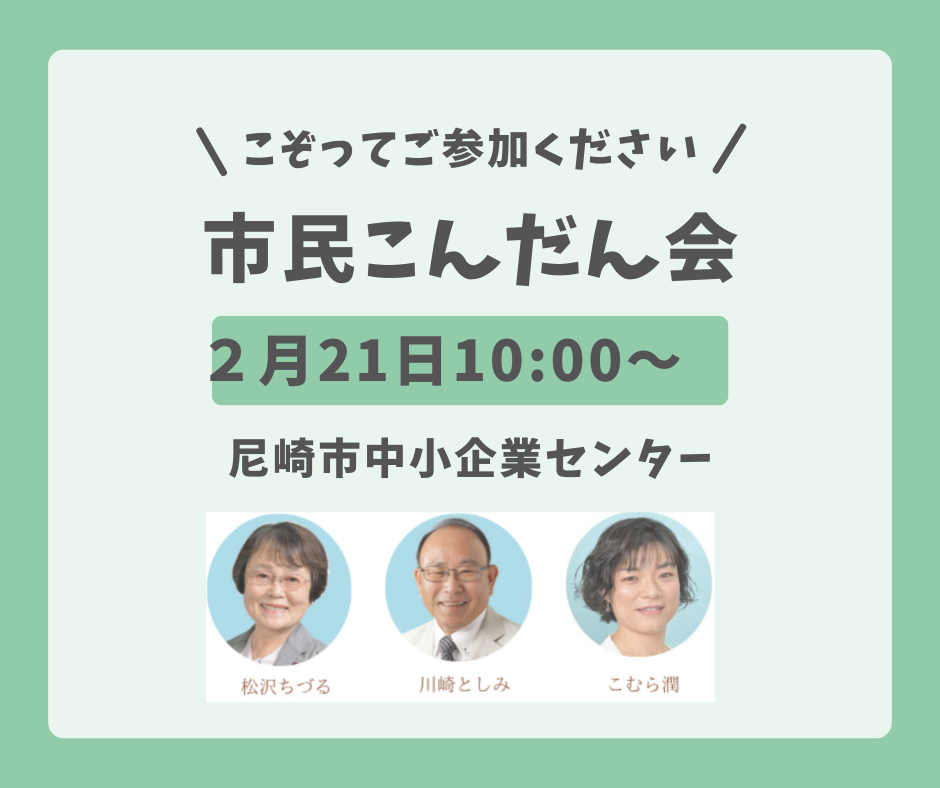消費税の減税
ただちに国会で議論すべきだ
高市早苗首相が、総選挙後の記者会見で9日、「2年に限り飲食料品の消費税率をゼロとすることについて、国民会議でスケジュールや財源などの課題の検討を進める」と述べ、「給付付き税額控除と合わせて議論し結論を得たい。夏前には中間とりまとめを行いたい」という考えを示しました。
しかし、議論をするなら、わざわざ「国民会議」を新設する必要はありません。国会にただちに法案を出して議論すべきです。
給付付き税額控除は、具体化の方向と内容によっては社会保障給付削減の口実にされるなどの懸念があるうえ、制度設計に時間がかかります。結局、消費税減税の実施の先送りになりかねません。また、同制度と引き換えに消費税が続くことになります。
■一律5%の減税を
総選挙ではチームみらいを除くほぼすべての政党が何らかの消費税減税を公約に掲げました。消費税減税の必要性では多数の合意があります。
日本共産党は「食料品ゼロ%」に頭から反対するものではありません。将来、消費税廃止への過程では、食料品など生活必需品の税率をゼロにすることもあり得ます。
しかし、食料品だけの消費税率ゼロは、飲食店が10%のままでは、売り上げが落ちるという不安の声も出ており、農家や漁家の農機具などの仕入れに支払った消費税をどう取り戻すかなどの対策に時間がかかります。また、2年間の限定では、2年後に大増税になります。
日本共産党は将来的な消費税廃止をめざし、緊急に一律5%の減税を提案します。準備期間は数カ月で可能で、物価高対策として効果的です。
財源をどうするかも重大な問題です。国債に頼れば円安を招き、物価高騰を引き起こします。
■大金持ちに課税を
消費税一律5%減税に必要な財源は16・3兆円です。日本共産党は、中小企業を除いて法人税率を28%にもどすことで4・3兆円、大企業優遇税制の廃止・縮減で10兆円、富裕層の株式譲渡所得・配当所得の課税強化の2・2兆円を財源にすることなどを要求しています。
1月26日の党首討論で日本共産党の田村智子委員長が「大企業の法人税をもとに戻す。あるいは富裕層、大株主にきちんと課税する」と述べたのに対し、日本維新の会の藤田文武共同代表は、「大企業・金持ちからがっつり取ろうと財源を明示していることは筋が通っている」と応じました。
高市首相は、先の会見で消費税減税の財源として、補助金や租税特別措置の見直し、税外収入をあげました。
しかし、2026年度の税制改正大綱では大企業優遇が多くを占める法人税の租税特別措置のうち、大企業向けの賃上げ減税の廃止が出される一方、研究開発減税は拡充、設備投資促進減税が新設されました。政府は、さらなる大企業減税を求める財界の意見には逆らえず従ったのです。
消費税減税のために大企業優遇税制をただすには大企業応援の政治から抜け出すことが不可欠です。
しんぶん赤旗 2026.2.14「潮流」欄より